必要とするすべての人に寄り添うケアを提供
「Cordaan」は、アムステルダムを中心に、そのほかオランダの120の場所と地域で、約20,000人にケアを提供している福祉団体。対象は子どもから高齢者まで、学習障害のある子どもや大人、精神疾患、知的障害、アルツハイマーの方など、精神的・身体的にケアやサポート、介護を必要とするすべての人に寄り添うケアを目的としている。
約6,000人の従業員と2,500人以上のボランティアが、あらゆる規模の介護者や介護・ケアの専門家、研究機関、多くの社会組織と協力し、アムステルダム最大級のケア団体として、市内のあらゆる場所に工房、グループホーム等の施設を運営していて、アート・チームは3名を中心とした15名のメンバーで運営している。
さまざまな場所や周辺の地域社会で、可能な限り自宅や「自宅と同じような場所」で、小規模なケアや援助を提供できるよう、人々が備えている能力を刺激し、自立し、自ら選択する権利を尊重し、自分自身を賞賛できるように促している。
誰もが可能な限り長い間、住み慣れた地域で自分で選んだ生活を送れるように最大限サポートをし、それが困難になったときには、安全でフレンドリーな介護施設に移るという選択肢がなければなりません。
Cordaanが掲げるキーワードは、「カラフル」「刺激的」「親しみやすい」「フレンドリー」「思いやりがある」「近くにある」です。 (Cordaarn公式サイトより)

Cordaanは地域の各所に、通所の工房や演劇スタジオがあり、美術館やアートスペースとも連携し、アートを取り入れた活動を多く行っている。オランダ初の取り組みとして、通所ができない利用者の家に芸術家を派遣し、そこで創作や鑑賞を行うという、特別なプログラムも取り入れている。
そのほか、障害のある人がスタッフとして働くカフェの運営や、障害のある人々が手づくりした作品やグッズをショップで販売し、得た収入を支援にしている。
色々な特性のある人が参加できる演劇プログラムや、グラフィックデザインを学べるスタジオ
Cordaarnが運営する演劇プログラムを行うスタジオでは、障害のあるユースや大人がそれぞれ自由に表現できるクラスを見学した。インストラクターのナビゲーションのもと、シンプルな小道具を活用ながらオノマトペなど決まった言語を使用せずに演じる即興のセッションなど、ひらかれた雰囲気の中で参加者が楽しみながら過ごす様子が見られた。
ちょうど私たちがアムステルダムを訪れた時期は「ミルクシェイク・フェスティヴァル」というイベントが行われており、Cordaarnの演劇プログラムに参加するダウン症や自閉症ほか色々な特性のあるユースたちも、このフェスティヴァルで披露するパフォーマンスの練習をしていた。ミルクシェイク・フェスティヴァルは、エレクトロニカ・ダンス・フェスティヴァルで、肌の色や性別、性自認、障害の有無ほかさまざまな枠組みを超えて誰もがつながり、国内外から多様なアーティストが集い、音楽やファッション、アートをつうじて表現するイベントだ。
また、同じ施設内には、デジタル技術を習得できるスタジオも併設されており、障害のある人たちが、映像や画像をデジタル加工し、仲間に共有する場所となっている。
大きな窓で開放感のあるスペースには、デジタルクラスの参加者たちの笑い声であふれていた。部屋にはこれまでにつくられた制作物が壁に貼られたり、机の上にポートフォリオとして置かれていて、それぞれの方法で自分自身を表現するデザインを、仲間たちと切磋琢磨しながら楽しんで続けている様子が伺えた。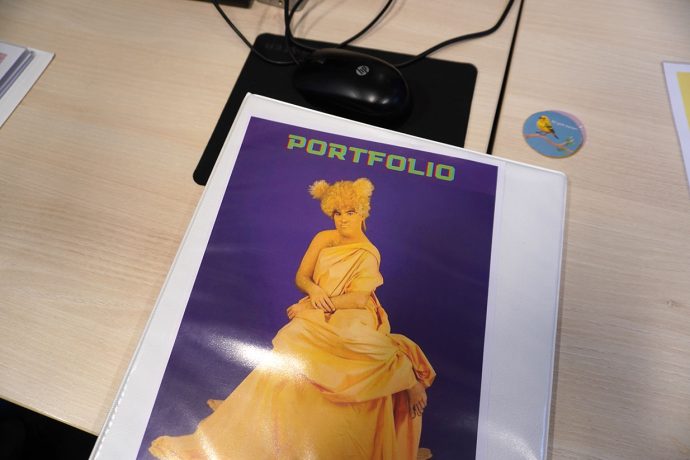
「個」を尊重しながら、それぞれの要望の実現と意思決定を大切にサポートする
Cordaarnスタッフによると、こうしたケアや表現のサポートで最も大事にしていることのひとつには、個人の意思や希望を尊重することだと言う。利用者はあらゆる悩みをソーシャルワーカーに相談できるよう、ひらかれたサービスを目指している。
もちろん個人によって相談ごとや要望は異なるが、基本「個」が希望することをサポートするシステムである。基本的に利用者はお金を支払わず参加でき、すべて国からの助成金によって賄っているという(国に政策提言をすることもあり)。
Cordaarnを訪れて、そこに過ごす人たちと触れ合いながら、ゆるやかな雰囲気の中にある貫かれたオランダのケアの思想を垣間みたような気がした。また、障害のある方の興味関心で参加できるダンスや演劇、絵の表現のクラスはとても素敵な雰囲気で、AITが協働しているダウン症や自閉症の子どもを中心とした絵の教室アトリエ・エーの空気感にも近しいものを感じた。Cordaarnの幅広いサポートシステムを知るためにはまだまだ継続的なリサーチが必要だが、今後も対話を続けていきたい。
テキスト・写真:藤井 理花

